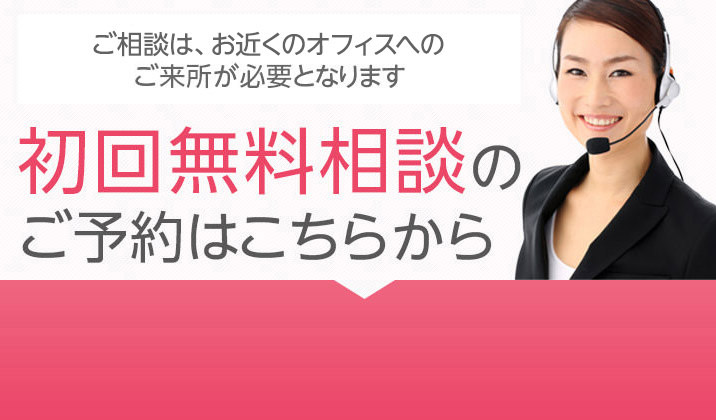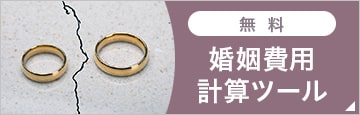和解離婚とは? メリット・デメリットや手続きの流れを弁護士が解説
- 離婚
- 和解離婚とは

愛知県がホームページ上で公開している「2023年愛知県の人口動態統計(確定数)の概況」によれば、愛知県の離婚件数は1万928組で、5年連続で減少しています。ただし離婚率は全国第15位であり、全国的にみれば離婚は多い状況です。
夫婦が離婚する場合、もっとも多い離婚方法は話し合いによる離婚ですが、話し合いや調停によっても離婚できない場合には、裁判手続きに進みます。裁判になった場合は、判決がでるまで争うイメージが強いかもしれませんが、裁判において双方が和解した場合は「和解離婚」が成立します。
本記事では、和解離婚の意味や他の離婚方法との違い、和解離婚をするメリット・デメリット、和解離婚が成立するまでの流れについて、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。


1、和解離婚とは? 調停離婚や認諾離婚との違い
「和解離婚」とは、離婚訴訟の訴訟継続中に裁判官の判決が出る前に、当事者同士の話し合い、または裁判官が和解を促す和解勧告に応じることで、離婚を成立させることです。
和解離婚とよく混同されるのが、「調停離婚」や「認諾離婚」です。
「調停離婚」とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して行う離婚方法のことです。夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合などに利用することができます。
日本は、調停前置主義が採用されているため、離婚裁判を提起するには原則調停を経る必要があります。調停離婚も、話し合いによりお互いが離婚や条件に合意する手続きではありますが、そもそも訴訟に至る前の手続きです。
「認諾離婚」とは、訴訟において被告(申し立てをされた側)が原告(申し立てをした側)の請求を全面的に受け入れて離婚することをいいます。
ただし、認諾離婚ができるのは、離婚のみを求めている場合です。離婚以外に親権・養育費・財産分与など離婚に付随する問題を訴えに含めている場合には、認諾離婚はできません(人事訴訟法第37条1項但書)。
また、和解離婚とは異なり、認諾離婚は被告のみが行うことができます。そして、請求を全面的に受け入れるという内容であるため、相互に譲り合って行う和解離婚とは異なります。
2、和解離婚のメリット・デメリット
和解離婚のメリットとデメリットをそれぞれ解説していきます。
-
(1)和解離婚のメリット
和解離婚は、財産分与や面会交流の内容などの離婚条件を話し合いによって柔軟に決定することができます。
お互いに妥協点をみつけて合意に至るので、判決によって強制的に条件が命じられる場合とは異なり、当事者双方が納得できる内容で決着できる可能性が高まります。
そのため、無理のない条件や余裕を持った条件でまとまることが多く、支払いがすぐに滞るという事態や、面会交流のトラブルなどを回避できる傾向があります。
また、一般的に裁判は判決がでるまで1年以上はかかりますが、和解離婚は当事者間で和解が成立さえすれば判決を待つ必要はないため、早期の解決が期待できるでしょう。 -
(2)和解離婚のデメリット
和解離婚では、当事者がお互いに譲り合って紛争を解決することになります。そのため、判決による結果よりも、ご自身にとって不利な条件で離婚が成立する可能性もあります。
ただし、判決になった場合には、結果の保障はありません。イチかバチかの賭けにでるよりも、和解離婚によって確実に条件を確定させる選択も十分にあり得ます。
3、和解離婚の流れ
和解離婚により離婚が成立するまでの流れは以下のとおりです。
- 訴訟の開始
- 第1回口頭弁論期日が開かれる
- 第2回以降の口頭弁論期日が開かれる
- 双方による話し合い
- 和解成立
- 裁判所による和解調書の作成
各工程を詳しく確認していきましょう。
-
(1)訴訟の開始
和解離婚は、離婚裁判内で行われる訴訟上の和解です。
調停が不成立となった後、訴訟を提起するためには、原告は以下の書類を裁判所に提出する必要があります。- 離婚裁判を求める訴状
- 請求原因を立証するための証拠
- 離婚調停が不成立になったことを示す「調停不成立証明書」
-
(2)口頭弁論期日が開かれる
原告の訴えの提起が適法に行われた場合、第1回口頭弁論期日が指定され、被告には答弁書の提出期限が通知されます。
口頭弁論期日では争点が整理され、当事者双方が証拠に基づいて主張・立証を行い、必要に応じて、2回目以降の弁論期日・弁論準備期日が指定されます。
なお、1回目の口頭弁論終了後は、和解に向けた話し合いを進めて問題ありません。 -
(3)和解勧告・当事者間で和解交渉
原告・被告がある程度、主張・立証を終えた段階で、裁判官から和解の勧告がなされることがあります。ただし、訴訟の経過から和解による解決が難しいと思われるときは、和解の勧告はなされない場合もあります。
一般的には、訴訟の経過や裁判官の心証を受けて、当事者間で和解交渉が行われます。双方条件に納得できれば和解は成立です。 -
(4)和解成立・裁判所による和解調書の作成
当事者間で決めた離婚条件は、和解調書に記載されます。
当事者の一方が、裁判所から送付された和解調書の謄本を市役所に提出することによって離婚が成立します。役所への提出期限は、和解が成立してから10日以内です。
4、離婚のトラブルを弁護士に相談するメリット
和解離婚になれば、判決を待つよりも、はやくかつ柔軟な条件で離婚が成立する可能性は高くなります。しかし、そもそも協議離婚や調停離婚の時点で離婚が成立していれば、訴訟を提起する必要もなく、新しい人生をスタートすることができたとも考えられます。
離婚をしようとしている夫婦が、当事者だけで話し合いを進めるのは簡単ではないですが、弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか。
ここでは、離婚トラブルを弁護士に相談するメリットを解説します。
-
(1)有利な条件で離婚を進めるためのアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、有利な条件で離婚を進められるようにアドバイスを受けることができます。
財産分与の内容や、慰謝料の金額の妥当性については、ご自身で判断するのは難しいでしょう。離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、ご自身の状況に応じて適切な行動をとれるように、法的なアドバイスやサポートを受けることが期待できます。 -
(2)代理人として相手との交渉を任せることができる
弁護士はご依頼者の方の代理人となれるので、依頼した時点から相手と直接やり取りをする必要がなくなります。
話せばケンカになってしまう、お互い意地になって妥協点が決まらないという状況では、建設的な話し合いは望めず、精神的なストレスも大きくなるでしょう。しかし、間に弁護士が入り、法的な見解を元に話し合いを進めることができれば、話し合いがまとまる可能性も高まります。 -
(3)離婚裁判の手続きを任せられる
訴訟になった場合には、弁護士に離婚裁判の手続きを任せることができます。
口頭弁論期日は平日の日中に開かれますが、和解する場合であっても、数回の期日を経ることが一般的です。争いが激しい場合には、1年以上かかることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として出廷することが可能です。また、裁判所に提出すべき書面や証拠についても、すべて弁護士が対応してくれるため、仕事や家事などへの影響を抑えつつ、離婚成立をサポートしてもらえます。
5、まとめ
和解離婚とは、離婚訴訟の訴訟継続中に裁判官の判決より先に、当事者同士の話し合いによって離婚を成立させる方法です。
和解離婚が成立し、和解調書が作成された場合には、原則としてその記載事項については後から覆すことはできません。そのため、和解の条件については弁護士と相談しながら慎重に判断するのが良いでしょう。
離婚訴訟や離婚トラブルでお悩みの方は、できるだけはやく弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスには、離婚トラブルの解決実績が豊富な弁護士が在籍しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています