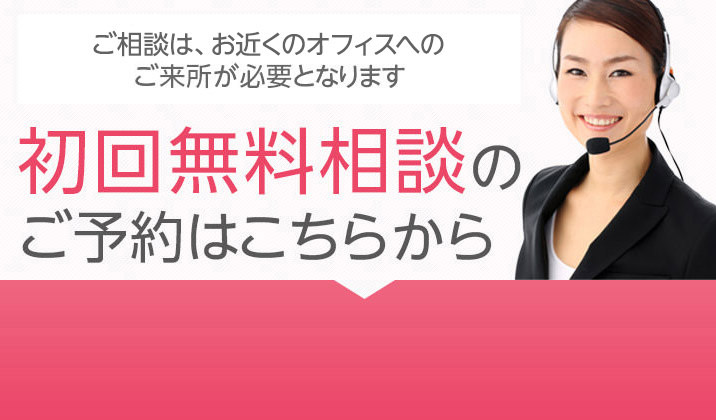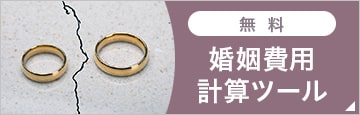監護義務とは? 親権との違いや権利者を分ける際の注意点を解説
- 親権
- 監護義務

子どもがいる際の離婚では、どちらが子どもの「親権」を持ち、「監護義務」を負うか決めます。
一般的には、親権者となった親が監護権を持ち、子どもと一緒に生活することになりますが、監護義務を負う親が子どもと一緒に生活するケースもあります。
今回は、そもそも監護権とは何か、決定の手続き、メリット・デメリット、事前に知っておくべきことについて、ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスの弁護士が解説します。
目次


1、監護義務とは
監護義務とはどのような義務なのでしょうか。以下では、監護義務の概要や監護権者を決定する手続きなどについて説明します。
-
(1)監護権・監護義務とは何か?
監護権・監護義務とは、子どもを監護・教育する権利義務をいいます(民法820条)。例えば、子どもがどこで生活するかを決めることができる権利である居所指定権(民法822条)や子どもが職業に就く際に親が同意する権利である職業許可権(民法823条)も監護権に含まれています。監護権・監護義務のことを一般的に「身上監護権」と表現することもあります。
-
(2)監護権者を決定する手続き
監護者を決定する手続きは、以下のようになっています。
① 夫婦の話し合い
監護権者を決定するには、まずは夫婦の話し合いによりどちらが監護権者になるかを決めます。夫婦の話し合いにより監護権者が決まれば離婚届を提出し、離婚成立となります。
ただし、離婚届には親権者の記載欄はあっても監護権者の記載欄はありません。親権と監護権をわけたときは、離婚協議書にその旨を記載しておきましょう。
② 調停・審判・裁判
当事者同士の話し合いで監護権者が決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
離婚前であれば離婚調停の中で話し合いを行い、調停で決まらなければ離婚訴訟で判断してもらうことになります。
離婚後であれば子の監護者の指定調停で話し合いを行い、調停で決まらないときは審判で判断してもらうことになります。 -
(3)監護義務を怠った場合はどうなるのか?
子どもの年齢にもよりますが、幼い子どもに対して、生存に必要となる監護を怠ったときは、保護責任者遺棄罪に問われる可能性があります(刑法218条)。保護責任者遺棄罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役と定められています。
また、監護義務を怠った親は、親権者または監護者として不適格と判断され、親権者や監護権者の変更が認められやすくなります。
2、監護権と親権の違い
監護権と親権は、どのような違いがあるのでしょうか。以下では、監護権と親権の違いや親権者を決める手続きについて説明します。
-
(1)監護権と親権の違いとは?
親権とは、親が子どもに対して有する身分上・財産上の権利義務の総称です。監護権は、親権の中に含まれる身上監護権にあたりますので、親権の中に含まれる権利義務のひとつと考えてもらえればよいでしょう。
親権は、子どものいる夫婦が離婚する際に必ず決めなければならない事項であるのに対して、監護権は必ず決めなければならない事項ではありません。特に定めない場合は、親権者が監護権も持つことになります。 -
(2)親権者を決める手続き
親権者を決める手続きは、基本的には、監護権者を決める場合の手続きと共通します。具体的には、以下のような手続きになります。
① 夫婦の話し合い
夫婦が離婚する際には、お互いの話し合いによりどちらを親権者に指定するかを決めなければなりません。
通常は親権者に指定された親が監護権を行使することになりますが、親権と監護権を分けて指定することも可能です。
② 調停・裁判
夫婦の話し合いでは決められないときは、家庭裁判所の離婚調停で話し合いを行います。調停で話し合いがまとまれば調停成立となり、夫婦の離婚や親権者が決定します。
他方、話し合いがまとまらなければ調停不成立となり、親権者は、離婚訴訟の手続きで裁判所に判断してもらうことになります。
3、監護権者と親権者を分けるメリット・デメリット
親権者と監護権者を分けることもできますが、それはどのようなケースで行われ、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。
-
(1)監護権者と親権者が分かれる例
親権者と監護権者は一緒の方が望ましいと考えられていますので、特に必要がない限りは、親権者と監護権者を別々にすることはありません。
親権者と監護権者を分けるケースとしては、主に以下のようなケースが想定されます。- 子ども名義の財産がある程度あり、一緒に生活する母親よりも父親の方が財産管理に向いているケース
- 事業を行っており、子どもを将来跡取りにしたいと考えているケース
- 離婚後も子どもと何らかのかかわりを持ちたいと考えているケース
-
(2)監護権者と親権者を分けるメリット
離婚時に対立が生じやすいのが、親権に関する問題です。
子どもがいる場合、離婚の合意ができたとしても親権者が決まらなければ離婚することができません。そのため、親権問題は離婚の争いが長期化する要因のひとつとなります。
こうしたことの打開策として親権と監護権を分ける方法が挙げられます。子どもに対する権利を分けることで、お互い納得して合意できる可能性が高まる、というメリットがあります。
また、親権者を父親、監護権者を母親にすることで、離婚後、養育費が支払われなくなるリスクを下げられるなどのメリットもあります。 -
(3)監護権者と親権者を分けるデメリット
子どもと一緒に生活する監護権者には、子どもの代理人となって契約などをすることができません。たとえば、子どもがスマートフォンを購入する場合には、親権者に連絡をして書類などに記載してもらわなければなりません。
このように親権者と監護権者を分けると、離婚後も元配偶者と定期的にかかわりを持たなければならないなどのデメリットがあります。
4、離婚する前に子どものことについて知っておくべきこと
子どもがいて離婚を考えている方は、子どものことについて、以下のことを知っておいた方がよいでしょう。
-
(1)親権者を決定しないと離婚届は受理されないこと
子どもがいる夫婦が離婚する際には、離婚の合意と親権者の指定が不可欠な要素となります。養育費、慰謝料、財産分与などは離婚後でも取り決めることができますが、親権者の指定に関しては、離婚届の必要的な記載事項となっていますので、離婚時に決定しなければ離婚届を受理してもらうことはできません。
-
(2)親権者と監護権者は後から変更できる
離婚時に親権者や監護権者を指定したとしても、その後、事情の変化が生じて親権者・監護権者がそのままでは不適切な状況となったときは、親権者・監護権者を変更することができます。
親権者の変更の場合、当事者同士の話し合いだけでは変更することができず、必ず家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てなければなりません。他方、監護権者の変更であれば当事者の話し合いより変更することも可能です。 -
(3)監護義務によって親権者に対して養育費を請求できる
一般的には親権と監護権は共通しますので、親権者に指定された親が子どもの養育費を請求することができます。
親権と監護権を分けた場合、親権者ではなく子どもと一緒に生活する監護権者が養育費を請求することになりますので注意が必要です。
お問い合わせください。
5、まとめ
監護義務とは、未成年の子どもに対して親が持つ権利義務であり、一般的には親権に含まれる権利義務のひとつです。通常は、親権と監護権はセットですが、親権と監護権を分けて決めることも可能です。
ただし、監護権者と親権者を分ける場合、メリットやデメリットを理解して慎重に判断することが大切です。また後々トラブルにならないよう、監護権に子どもに対するどのような権利が含まれているかしっかり把握することも重要です。
離婚時の親権獲得や監護権者を分けるべきか、離婚条件をどうするべきかなど、離婚に関してお悩みの方は、離婚問題の解決実績があるベリーベスト法律事務所 岡崎オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|